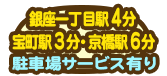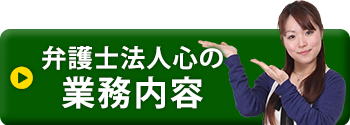過払い金
過払い金が発生する可能性がある人
1 過払い金が発生する可能性がある人について

結論から申し上げますと、過払い金が発生する可能性がある人とは、貸金業者やクレジットカード会社から、利息制限法という法律で定められた上限金利を超えた金利で借入れと返済をしていた方です。
もし利息制限法で定められた上限を超えた利率が定められていて、実際にその利率に基づく利息を支払ったとしても、上限利率に基づく利息を超えて支払って部分については、法律上無効なものとなり、貸金業者等に返還を求めることができます(不当利得返還請求)。
この上限利率に基づく利息を超えて支払って部分が、一般的に過払い金と呼ばれています。
以下、過払い金の返還を求めることができる可能性があるケースについて、具体的に説明します。
2 平成18年よりも前から借入れと返済をしていた
平成18年(2006年)、利息制限法の上限を超えた利率を設定していた場合において、当該利率に基づいて支払われた利息のうち、上限利率を上回る部分については、事実上すべて無効になるという最高裁判所の判決がなされました。
この最高裁判決を受けて、利息制限法の上限を超えた利率を設定していた多くの貸金業者、クレジットカード会社は、一斉に利息制限法の上限以下の利息に改めたようです。
(実際に取引履歴などを見ると、平成18年に、利率を改めるための契約変更の履歴が載っていることが多いです)
そのため、一般的には、平成18年以前から借入れと返済をしていた場合には、利息制限法の上限を超えた利率に基づく利息を支払っていた可能性がありますので、過払い金が発生している可能性があります。
3 過払い金返還請求権の消滅時効が完成していない
2020年4月に民法が改正されたことにより、過払い金の返還を求めることができる権利は、「権利を行使することができる時」すなわち最後の取引(完済)から10年、または「権利を行使することができることを知った時」から5年で時効により消滅します。
【参考条文】(民法)
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
(第2項以下略)
ただし、経過措置として、「施行日前に債権が生じた場合におけるその債権の消滅時効の期間については、なお従前の例による。」と定められています。
そのため、少なくとも2020年4月1日より前に完済し、過払い金が発生していた場合には、「施行日前に債権が生じた場合」に該当するため、消滅時効は完済した日から10年を経過することで完成すると考えられます。
過払い金の相談に必要となる資料
1 過払い金のご相談の際に必要となる資料について

結論から申し上げますと、過払い金の返還請求の相談をする際に最低限必要なのは、どの貸金業者等から借入れをしていたか(または現在しているか)という情報のみです。
絶対に必要となる資料はありません。
相談の段階においては、すでに完済している場合には、どの貸金業者やクレジットカード会社から借入れをしていたかについて、記憶に残っている範囲で結構ですのでお話しいただくことができれば、過払い金の調査や返還請求は可能です。
なお、過払い金返還請求に限らないことですが、弁護士に事件の依頼をする場合には身分証明書や契約書作成のために印鑑等は必要になります。
以下、かつて借り入れをしていた(または現在借り入れている)貸金業者等の情報以外に、ご相談にご用意いただくことで、より早く正確に過払い金の調査や返還請求ができるようになる資料について説明します。
2 借入れをしていた(している)貸金業者、クレジットカード会社のカード
もしお手元にあるのであれば、貸金業者やクレジットカード会社のカードをお持ちいただくと、借入れをしていた(現在している)貸金業者等を正確に把握することができます。
カードが発行されていない場合や、アプリに切り替えている場合には、スマホでアプリの画面を見せていただいても差し支えありません。
これにより、記憶違い等により、本当は借入をしていなかった貸金業者等に対する調査をしてしまうことを予防することができます。
その結果、過払い金の調査、返還請求に余分な時間を要することを防ぐことができます。
3 借入れをしていた(している)貸金業者、クレジットカード会社の取引履歴
貸金業者やクレジットカード会社の取引履歴を取得されているのであれば、ご提供いただくと、過払い金を算定するための引き直し計算を迅速に行うことができます。
取引履歴がない場合には、弁護士が過払い金返還請求の依頼を受け、貸金業者等に対して取引履歴の開示を求めることができます。
そして、取引履歴の開示を受けた後、弁護士が引き直し計算を行い、過払い金の有無の調査や過払い金の金額を計算するという流れになります。
4 借入れをしていた(している)貸金業者、クレジットカード会社の契約書
必ず使用するというわけではありませんが、過払い金の返還請求に関して、争点(貸金業者等が過払い金の返還を拒絶する事由)の存在が存在する場合には、契約書の内容が問題になることもあります。
そのため、争点が存在し、訴訟の提起等を検討する必要がある場合においては、契約書があるとより綿密な検討をすることができる場合もあります。
過払い金の請求にかかる期間
1 過払い金の請求をした際に要する期間の概要

貸金業者等に過払い金の返還請求をし、支払いを受けるまでにかかる期間は、一般的には6か月~1年半程度となります。
任意交渉で和解をする場合と、任意交渉では和解できず訴訟を提起する場合とで、支払いを受けるまでにかかる期間は大きく異なります。
任意交渉の場合、弁護士に依頼してから、貸金業者等から過払い金の返還を受けるまでの期間は、一般的には6か月程度です。
任意交渉では解決できず、過払い金返還請求訴訟を提起する場合には、訴訟提起の準備から過払い金の返還を受けるまでの期間は、一般的には6か月~1年程度です。
以下、詳しく説明します。
2 任意交渉の場合
過払い金の返還請求は、一般的には次の順番で行います。
①貸金業者等から取引履歴を取得する
②取引履歴をもとに引き直し計算をして過払い金を算定する
③貸金業者等に対し裁判外で過払い金の返還を請求する
④貸金業者等と支払金額等について交渉し和解契約を締結する
⑤和解契約で定めた金銭が貸金業者等から入金される
①には約1か月、②にも約1か月を必要とします。
③、④については、一般的には2週間から1か月程度を要します。
⑤については、和解契約成立の日から1~3か月後となることが多いです。
3 訴訟を提起する場合
任意交渉をしても返還金額や返還時期について合意ができない場合や、争点(過払い金を返還する義務がないと主張することができる事実)が存在し、貸金業者等が返還に応じない場合には、訴訟を提起して過払い金の返還請求をすることになります。
訴訟の流れは次のとおりです。
①訴訟提起の準備~訴訟の提起
②裁判所で第1回期日を行う
③被告の貸金業者等から和解の連絡を受け裁判外で交渉をする
(④ 交渉がまとまった場合、訴外または第2回期日で和解をして終了)
⑤交渉がまとまらない場合、第2回以降の期日を経て判決
⑥貸金業者等から過払い金の支払を受ける
①については、取引履歴があれば、2週間~1か月程でできます。
②については、一般的には訴訟提起後1か月~1か月半後程度に行われます。
③、④については、第2回期日は第1回期日の1~1か月半後に設定されることが多いため、その間に実施されます。
⑤については、第2回期日を経て判決がなされ、判決文が送達されるまで、1か月程度を要することがあります。
⑥については、和解契約成立の日または判決文送達から1~3か月後となることが多いです
争点がない場合には、訴訟提起の準備から過払い金の返還を受けるまでの期間は、一般的には半年~1年程度です。
争点が存在し、過払い金の返金を拒否されている場合、争点の内容等によっては期日が5回以上開催されることもあり、判決まで1年以上の期間を要することもあります。