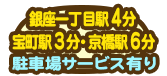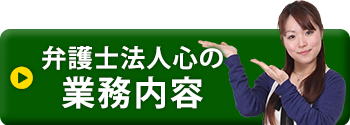高次脳機能障害となり働けなくなった場合、相手方にどのような請求をすることができますか?
1 はじめに
治療期間中であれば休業損害を請求することができます。
治療が終了し、高次脳機能障害による後遺障害が認定された場合には、逸失利益を請求することができます。
高次脳機能障害となった場合、仕事及び日常生活に支障が出ることが多いです。
これにより、仕事による収入が得られなかったり減少した場合、治療中の期間であれば休業損害に対する賠償を、後遺障害が認定された後であれば逸失利益に対する賠償を、それぞれ事故の相手方に請求することができます。
2 休業損害について
治療期間中の場合、休業損害を請求することになります。
⑴ お勤めの方の場合
お勤めの方であれば、お勤め先に休業損害証明書を作成してもらい、これに基づいて請求します。
⑵ 自営業の方の場合
自営業の方の場合は、収入資料に基づいて1日当たりの収入金額を算定し、これに基づいて請求します。
燃料費などの経費がある場合は、収入金額から経費を差し引いた金額(実際の利益)に基づいて損害額を算定します。
保険会社との間では、所得税の申告書記載の金額が重視されますので、収入の資料をそろえることのほかに、所得税の申告をきちんとしておくことも大事です。
⑶ 休業の必要性(仕事への支障の有無、程度)についての立証について
高次脳機能障害といっても、その具体的な症状や、仕事への支障の有無・程度は被害者の方ごとに異なります。
また、お仕事の内容によって、休業の必要性の有無が変わってきます。
このため、休業損害を請求する際には、被害者の方の症状と、お仕事の内容を具体的に示して、休業の必要性について明らかにする必要があります。
3 逸失利益について
高次脳機能障害による後遺障害が認定された場合、後遺障害の程度に応じた後遺障害の等級が認定されます。
そして、各等級には、目安となる労働能力喪失率が定められています。
逸失利益は、後遺障害により労働能力が低下し、労働による収入が減少したことに対する賠償ですが、この算定に当たっては、被害者の年収に、労働能力喪失率を乗じて算定するのが一般的です。
しかし、事案によっては、所定の労働能力喪失率よりも低い喪失率とすべきではないか、後遺障害が認定されたが実際には収入の減少は生じていないのではないかといった問題が生じることがあります。
このような場合には、休業損害のところでお伝えしたのと同様に、症状や仕事の内容、仕事への影響を具体的に明らかにする必要があります。
4 おわりに
休業損害及び逸失利益の請求に際しては、いろいろ難しい問題が生じることがあります。
このようなときは、一度弁護士にご相談ください。
後遺障害の異議申立てに関するQ&A 自損事故でむちうちになった場合に使える保険には何がありますか?