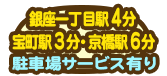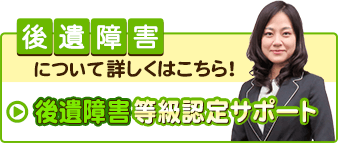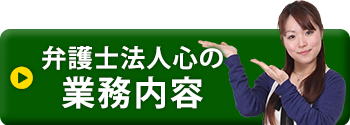後遺障害で弁護士をお探しの方へ

1 後遺障害についてお悩みの方は弁護士へ
事故のケガが完全に治りきらず、痛み等が残ってしまった際は、後遺障害の申請を検討することになります。
後遺障害の等級が認定されれば、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益等を請求することができるようになります。
後遺障害の申請を行う際は様々な点に注意が必要ですので、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
2 適切な後遺障害等級を獲得することの重要性
後遺障害が残るということは、体のどこかに障害が残っているということです。
むちうちであれば、痛みやしびれがずっと残ってしまっていたり、可動域制限であれば、動く範囲が制限されていたりと、後遺障害の内容によって様々です。
その後遺障害の内容に応じて、適切な後遺障害の等級が認定されれば、適切な賠償金額を受け取ることができますが、もし適切な等級が認定されていない場合には、賠償金が数百万円、場合によっては数千万円以上も変わってしまうことがあります。
これは、決して大げさに表現しているものではありません。
3 受け取れる賠償金額
具体的な金額について、むちうち(14級9号)を例にしてご説明します。
⑴ 14級の後遺障害慰謝料
裁判基準の後遺障害慰謝料は、14級の場合、110万円です。
⑵ 後遺障害逸失利益
むちうち14級の場合の労働能力喪失率は5%でまとまることが多いです。
労働能力喪失期間は、3~5年ですが、ここでは5年で計算してみます。
基礎収入が500万円の方の場合、後遺障害逸失利益は、約114万円となります。
【計算式】
500万円×5%×4.5797(※1)=114万4925円
※1 5年に対応するライプニッツ係数
⑶ 後遺障害14級の賠償金額合計
むちうちで14級が認定されますと、後遺障害慰謝料110万円、後遺障害逸失利益約114万円、合計約224万円の賠償金を受け取れる可能性があります。
もし、14級が認定されなかった場合には、約224万円も損してしまう可能性があるということです。
4 後遺障害に詳しい弁護士選びの重要性
適切な後遺障害等級が認定されていない場合、前述したように、最低等級である14級でさえ、約224万円も損してしまう可能性があるわけです。
等級が高くなれば高くなるほど、損してしまう金額が増えていきます。
そうすると、いかに適切な後遺障害等級を獲得しておくことが重要であるかがわかると思います。
当法人では、メインの取り扱い分野を交通事故分野に絞っている弁護士と、後遺障害等級認定審査機関である損害保険料率算出機構出身のスタッフや自賠責調査事務所のスタッフ、元損保会社の社員、元損保会社の顧問弁護士であった弁護士などで交通事故チームを編成し、集中的に後遺障害案件を取り扱っています。
そのため、本来認定されるべき後遺障害等級を逃さないようにするためには、どのように通院していくのが望ましいかなどのアドバイスができる知識、ノウハウを有しています。
適切な後遺障害等級が認定されるよう、後遺障害の申請は当法人にご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
弁護士に依頼する際の着手金 後遺障害における慰謝料と逸失利益について
後遺障害の認定結果に不服がある場合
1 後遺障害の認定結果に不服がある場合の具体例

後遺障害の申請をした結果、被害者が考える等級より低い等級が認定されることがあります。
例えば、事故により腰椎捻挫となり、腰椎捻挫に伴う神経症状(腰痛と下肢のしびれ)について「局部に神経症状を残すもの」として後遺障害14級9号に該当すると判断された結果に対し、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として後遺障害12級3号に該当すると考えるケースです。
また、①右大腿骨頚部骨折に伴う右股関節の可動域制限について「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として後遺障害10級11号に該当すると判断された結果に対し、①に加えて②右鎖骨近位端骨折に伴う右鎖骨の変形障害について「鎖骨に著しい変形障害を残すもの」として後遺障害12級5号にも該当するから、①と②を併合して9級になると考えるケースです。
2 後遺障害認定の結果に不服がある場合に取り得る手段
後遺障認定の結果に不服がある場合、被害者が考える後遺障害に該当することを裏付ける新たな資料(証拠)を入手して、①自賠責保険会社(共済組合)に対して異議申立をする、②自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行う、③裁判所に訴訟提起する、という3つの手段があります。
3 ①自賠責保険会社(共済組合)に対して異議申立をする場合
前回の申請時より慎重かつ客観的な判断が求められるため、原則、損害保険料率算出機構に設置された自賠責保険(共済)審査会において、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議に参加して審査が行われます。
4 ②自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行う場合
自賠責保険・共済紛争処理機構は、被害者と自賠責保険会社(共済組合)との間で生じた紛争を処理(調停)する第三者機関です。
専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者からなる紛争処理委員会が、公正・中立な立場から、自賠責保険会社(共済組合)の結果の適否について審査します。
自賠責保険会社(共済組合)は、約款に紛争処理機構の審査結果を遵守すると定めているため、紛争処理委員会の審査結果に従って自賠責保険金(共済金)を支払います。
5 ③裁判所に訴訟提起する
①異議申立や②紛争処理を申請しても前回の結果が変わらない場合、最後の手段として、③訴訟を提起して裁判上で争うことがあります。
裁判所は、専門的知見を有する学者や専門医が審査した結果を重視する傾向にあるため、被害者が考える後遺障害等級に該当することを証明し得る新たな医学的証拠(医師の意見書等)を獲得することが肝要です。
どのタイミングで後遺障害申請を弁護士に相談するのがよいか
1 まず事故直後に相談する

交通事故被害に遭い、ケガの状況から後遺障害の可能性があると感じた場合には、できるだけ早く弁護士に相談するようにしましょう。
交通事故によるケガについて、医師に症状がきちんと伝わっていなかったり、必要な検査を受けていなかったりすると、後日、ケガが事故によるものと特定できないと判断されてしまうことがあるため、早期に弁護士に相談して、通院や検査等について適切なアドバイスを受けることが極めて重要になります。
2 通院中に相談する
交通事故によるケガで通院中に、症状が改善しなかったり痛みが続いたりした場合、後遺障害の可能性があると思った場合には、通院途中の早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害の申請の可能性がある場合、症状に応じて適切に通院することや必要な検査を受けることが大切になります。
通院中に弁護士に相談することによって、後遺障害の申請を視野に入れた適切な対応等についてアドバイスを受けることができると思います。
3 後遺障害診断書作成前に相談する
交通事故によるケガについて後遺障害の申請を行う場合、医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に弁護士に相談することをお勧めします。
後遺障害診断書の作成にあたっては、後遺障害の内容や症状に応じて、必要な検査を行ってもらったうえで、必要な事項を適切に記載してもらうことが重要となります。
弁護士に相談することによって、適切な後遺障害診断書の作成についてのアドバイスを受けることができると思います。