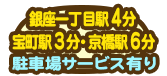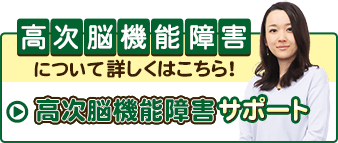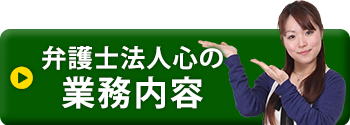高次脳機能障害で弁護士をお探しの方へ

1 高次脳機能障害のご相談
交通事故で頭を強く打つなどして、高次脳機能障害になってしまうことがあります。
高次脳機能障害となってしまったとき、今後どのような手続きを行えばいいのか、損害賠償はどうなるのか等、疑問に思うこともあるかと思います。
そのようなときは、一度弁護士にご相談ください。
2 弁護士選びは慎重に
高次脳機能障害案件の賠償金は、過失が低ければ、数千万円台が多くなってきます。
被害者の年齢が低ければ低いほど、被害者の基礎収入が高ければ高いほど、後遺障害認定等級が高ければ高いほど、被害者の過失割合が低ければ低いほど、より賠償金額は高くなります。
賠償金額がいくらでまとめられるかは、弁護士の力量次第です。
医者もそうですが、どの医者に頼んでも治療結果は同じということはなく、高次脳機能障害案件は、まさに弁護士の力量によって賠償金額にかなりの差が生じてくることがある案件なのです。
3 なぜ弁護士によって賠償金額に差が生じてくるのか
⑴ 認定等級
高次脳機能障害等級は、1級、2級、3級、5級、7級、9級とあり、1つ等級が違うだけでも、賠償金が数百万円~数千万円と違ってくることが通常です。
そのため、本来認定されるべき等級が認定されなければ、賠償金を数百万円~数千万円損してしまうといった事態が発生してしまうのです。
本来認定されるべき等級は、しっかりと後遺障害申請前に準備しておかないと獲得できる可能性が低くなってしまうこともありますので注意が必要です。
特に、後遺障害診断書等の書類作成時には、注意すべき点がいくつかありますので、その点を踏まえて準備しなければなりません。
その点を熟知している弁護士に任せなければ、適切な高次脳機能障害等級が認定される可能性が低くなってしまう可能性があります。
⑵ 示談交渉
ア 過失割合
賠償総額が数千万円の案件では、過失が5%違うだけでも数百万円違ってくることがあります。
そのため、過失割合について、被害者有利に交渉できる材料が少しでもある場合には、きっちりと過失割合の交渉までしてくれる弁護士を探してください。
イ 後遺障慰謝料
後遺障害慰謝料についても、示談段階でも、弁護士の交渉次第によっては裁判基準の満額の賠償を受けることができますので、この点も、特に理由がないのに安易に裁判基準の8~9割でまとめてしまわないような弁護士を探す必要があります。
また、等級によって、後遺障害慰謝料の金額も異なりますので、適切な等級認定がなされていることがかなり重要となってきます。
例えば、9級の場合の後遺障害慰謝料の裁判(赤本)基準満額は690万円ですが、7級ですと1000万円で310万円も違いますし、5級では1400万円ですので、7級とは400万円も違います。
このようにワンランク等級が違うだけで、後遺障害慰謝料だけでも数百万円も金額が異なってくるのです。
ウ 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益についても、争点となりやすい項目としては、①基礎収入、②労働能力喪失率があります。
①基礎収入については、自営業の方は固定経費をどこまで所得に加算するのか、事故前年度の収入が事情により極端に低い方などは、交渉して通常の年収にひきあげて算定されるような交渉が必要となってきます。
②労働能力喪失率については、高次脳機能障害以外にも、外貌醜状や可動域制限などで等級がついて、高次脳機能障害の等級が繰り上がって併合等級となっている場合などには、争われやすいため、この点についても、弁護士を介入させての交渉をおすすめします。
4 解決実績が豊富な弁護士へご相談ください
高次脳機能障害案件は、年々減少しており、取り扱ったことのある弁護士の数も実はそこまで多くないのが現状です。
その中でも、当法人の交通事故担当弁護士は、高次脳機能障害案件を得意とする弁護士が複数おりますので、安心してご相談ください。
後遺障害申請と症状固定について 高次脳機能障害が疑われるときはどうすればよいか
高次脳機能障害について弁護士に相談すると裁判になるのか
1 裁判ではなく示談による解決を目指します

弁護士に相談すると裁判になるというイメージを抱く方がいらっしゃいます。
しかし、高次脳機能障害について弁護士に相談したり、賠償金の請求を弁護士に依頼しても、必ずしも裁判になるわけではありません。
むしろ、高次脳機能障害について弁護士に依頼しても、裁判することなく示談で解決するケースのほうが多いです。
一般的には、まずは、話合いによって示談することを目指し、加害者側の提示額に納得がいかないとき、最終手段として裁判するという流れになります。
なぜなら、裁判になると解決までに長い期間を要したり、裁判費用や弁護士費用がかかるうえ、被害者の主張を裏付ける証拠が乏しい場合は、裁判をしても納得のいく請求額が認められるとは限らないからです。
2 高次脳機能障害について裁判になるケース
高次脳機能障害について裁判になる典型例は、被害者側の請求額と加害者側の提示額に大きな隔たりがあり、裁判を起こしたほうが獲得できる賠償金が多額になる可能性が高い場合です。
高次脳機能障害の等級は、症状の内容や程度によって、1級1号、2級1号、3級3号、5級2号、7級4号、9級10号など、細かく分かれています。
自賠責保険会社や任意保険会社から支払われる金額は、認定される等級に応じて、数百万円、数千万円単位で差が生じます。
そのため、高次脳機能障害の等級が争点となった場合(被害者と加害者が異なる等級を主張する場合)に、請求額と提示額に大きな隔たりが生じがちです。
3 弁護士法人ご相談ください
このように、高次脳機能障害について弁護士に相談すると裁判になるのではなく、弁護士は、自賠責保険会社の認定結果、加害者側の提示額の有無と金額、証拠の有無、争点の内容、弁護士費用特約の有無等、ご相談者の状況を考慮して、最善の解決策をアドバイスします。
また、最終的に裁判するかどうかは、弁護士とご相談者が打合せをした上で決定します。
高次脳機能障害は、専門的な内容を含む障害であって、適正な等級認定を受けたり、適切な賠償金を獲得するためには、高次脳機能障害を含む交通事故に詳しい弁護士に、できるだけ早く相談することをおすすめします。
高次脳機能障害について
1 高次脳機能障害とは

交通事故等が原因で脳外傷を負った場合、記憶・記銘力障害、集中力障害、遂行機能障害、判断力低下などの認知障害や、性格が攻撃的になり暴言を吐いたり、起りやすくなるなどの人格の変化を引き起こすことがあります。
脳外傷によるこれらの変化のことを、高次脳機能障害といいます。
高次脳機能障害が生じると、判断能力の低下などが原因でそれまでの仕事をこなすことができなくなったり、怒りっぽくなったことで家族との関係が悪化するなど、仕事や日常生活に著しい支障が生じます。
2 高次脳機能障害と自賠責保険の後遺障害
交通事故による脳外傷が原因で高次脳機能障害を発症した場合、自賠責保険の後遺障害認定を受けることができます。
後遺障害の認定を受けることができれば、その等級に応じた損害賠償を請求することができるため、障害の影響で仕事や日常生活に生じた損害を補填することができます。
ところが、高次脳機能障害の後遺障害申請の際、後遺障害診断書等の記載が原因で、症状が軽いと誤解されてしまうと、後遺障害の等級が低めに認定されてしまうため、障害の程度にふさわしい補償を受けることができなくなってしまいます。
3 高次脳機能障害のご相談は弁護士法人心へ
弁護士法人心には、後遺障害を判断する損害保険料率算出機構において、後遺障害認定実務に携わっていたスタッフが在籍しており、後遺障害申請に関する豊富なノウハウを有しています。
当法人では、内部研修を通じて、高次脳機能障害の申請にあたり、症状が軽いと誤解されてしまうポイントや、申請に際して周囲のご家族が気を付けなければならない変化等の情報を共有しています。
被害者様が事故に遭われた直後にご相談いただけましたら、治療開始から後遺障害の申請、損害賠償の請求にいたるまで、一貫した対応をさせていただくことができます。
交通事故が原因で脳外傷を負われた方やそのご家族がございましたら、是非、弁護士法人心 銀座法律事務所までお問い合わせください。